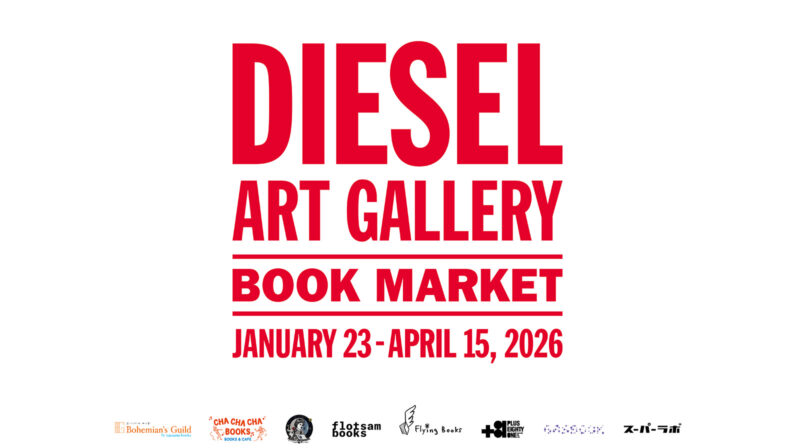リシャール・ジョフロワは1990年から、およそ30年間「ドン ペリニヨン」の醸造最高責任者を務めた人物。2019年、「ドン ペリニヨン」を離れたこのワイン界のリヴィング・レジェンドが「日本で日本酒を造っているらしい」と噂されたとき、多くの日本のワイン業界人は「意外」というよりも「やっぱり」と捉えたことをいまも覚えている。
『IWA5』。 2020年、そう名付けられて登場したリシャール・ジョフロワの日本酒は、2022年までにすでに3作が造られ、4作目、5作目が、リリースを待っている。IWA5が継続性をもったプロジェクトであることが疑いなくなった今、リシャールが日本酒を造る理由に耳を傾けよう。

フランス・シャンパーニュ地方ヴェルテュ村のワイン醸造を営む家系に生まれる。大学で医学を修め、博士号を持つ。ワインの道を志してからは、カリフォルニアの「ドメーヌ・シャンドン」でプロとしてのキャリアをスタート。1990年に「ドン ペリニヨン」醸造最高責任者に就任。その後、28年間のキャリアで「ドン ペリニヨン」の不動の地位を確立した後、退任し、その座をヴァンサン・シャプロンへと引き継いだ。2019年、「株式会社白岩」を富山県立山町白岩に設立。『IWA5』と名付けた日本酒を毎年造り続けている。
IWA5の使命
「2022年末、私はアメリカにいた。『IWA5』のハンド・セリングのために。そして、この旅のメインイベントとして、カリフォルニアの「Single Thread」、ニューヨークの「Eleven Madison Park」、そして「Jungsik」の3つのレストランでの『アッサンブラージュ1』から『3』までの3種類の『IWA5』の垂直ペアリングを仕掛けた……もう、それが、素晴らしすぎてぶっ飛んだよ!」
リシャール・ジョフロワはそう熱っぽく語った。
『IWA5』は第一作目『アッサンブラージュ1』が2019年に製造され、2020年にリリースされた。そこから2020年製造の『IWA5 アッサンブラージュ2』、2021年製造の『IWA5 アッサンブラージュ3』と造られ続け、2023年の夏前には2022年製造の『IWA5 アッサンブラージュ4』のリリースが予定されている。
「これまでの経験で明らかなのは、世界は日本酒を切望しているということだ。私の知るあらゆる酒のなかで、日本酒は最高峰の酒だ。これほど素晴らしい酒が他の酒の後塵を拝する理由はない」
1970年初頭、日本に3000以上あった日本酒蔵は、いまや1200蔵近くまで減っている。そのきっかけは、輸入酒が日本市場を席巻したためだと言われている。
「それはフェアじゃない。日本酒はもっと世界に出ていくべきなんだ。私は日本酒の素晴らしさを世界に伝えたい。そういう日本酒を造りたい。それが『IWA5』のミッションだ」
リシャール・ジョフロワの話はそう始まった。
自由を求め日本酒に至る
日本酒の何がそれほどまでに、この人物を惹きつけるのかは、ドン ペリニヨン時代からリシャールを知る人ならば、なんとなく想像がつくはずだ。
この人物のワイン造りには、一貫した哲学がある。それは、相反する要素の間にとられた厳密なバランスが、酒をより高い次元に至らせる、というものだ。陰には陽を。陽には陰を。ワインであれば、酸味が強いワインと甘みの強いワインをブレンド(=アッサンブラージュ)する。力強いワインには繊細なワインを。冒険的なワインには保守的なワインを。
リシャールのワインは、そのようなブレンドは、組み合わされるそれぞれのワインの長所を打ち消し合うようなことにはならない、という事実を証明している。むしろ、バランスを保ちながら、ワインは静謐にして雄弁なる高みへと登っていく。それはあたかも、ヘーゲルの言う弁証法の止揚(アウフヘーベン)のように。

アッサンブラージュにアッサンブラージュを重ねていくワイン造りは、まるで複雑機械式時計を作るように精密だ。ところが、ワインの場合、時計であれば歯車にあたるブドウが、気まぐれな自然の影響を大きく受け、年によって、場所によって変化してしまう。
「リシャール・ジョフロワは、実は、不確定要素がより少ない素材で、もっと厳密に酒を造りたいのではないか?」 リシャールを知る人々の間には、そんな予感と期待があったはずだ。
「そうだ。それこそが、私が日本酒造りを始めた原点だ。もちろん、私が日本を愛しているということ、そして、日本にたくさんの友人がいることも理由ではある。しかし、もっと私自身のわがままでパーソナルな動機は、一人の造り手として、より自由に自分の旅を続けたい、ということなんだ」
リシャールは、ワインはどんなに技術的な介入の度合いが大きくなっても、50%以上はブドウで決まるという。
「ワインは息苦しい。母なる自然、気候条件、ヴィンテージ(収穫年)に影響される。それにA.O.C.のようなシステムもある。たくさんの制限があり、身動きが取れないとすら言ってもいいとおもう。それに比べて日本酒は驚くほど自由だ。日本酒が伝統に縛られ、不自由だとおもっている人は少なくないが、それは誤解だ」
私がどれほど自由か「白岩」に来てみればわかる。と老獪に微笑む。
日本酒のテロワール
「白岩」は『IWA5』を造る会社の名前であり、富山にある酒蔵だ。自由を求める醸造家の日本酒づくりの舞台は、たまたま、富山だったのか? あるいは富山には何らかの地理的な要因、ワインで言うところのテロワールがあり、富山である必要があったのか?
「ワインにブドウが果たす役割を考え、日本酒における米の役割を語るのであれば、日本酒に与える米の影響はせいぜい25%程度に過ぎない。そういうワインの後追い的発想を日本酒に持ち込むことを、私はいいとはおもっていない」
リシャールは「ワインには400年程度の歴史しかない」と言う。実際、リシャールが人生の長い時間を捧げた発泡するワインとしてのシャンパーニュの歴史は、1600年代前半に始まっていると言っていいだろう。しかも、400年前のシャンパーニュというのは、本当に原初の姿であり、現代のそれとは多分に違ったワインだったと考えられている。現代を生きる我々が、ワインと言ってイメージする形のワインの歴史はといえば、おそらくそれはもっとずっと短く、100年にも満たないのではないか?
「日本酒にはもっとずっと長い歴史がある。ならば日本酒がワインを学ぶより、ワインが日本酒から学ぶことの方が多いのではないだろうか?」
そのうえで、とリシャールは続ける
「日本酒にテロワールを言うのであれば、それは蔵だ」
水でも酵母でもなく? と問うと
「水も結局、蔵の下を流れているものだろう? 酵母、というよりも 酛(もと。リシャールもMotoと表現。発酵を行う細菌が生育する環境、あるいは特定の環境において生きる細菌)だって、蔵のマクロバイオロジーじゃないか? 酒質とキャラクターを決めるものは、造りだ。それは、杜氏、蔵のレイアウト、設備……実際、似たような形の蔵は似たような酒を造るんじゃないだろうか?」
『IWA5』の場合、それはIWA5のために建造された独特な蔵。2022年に完成した、リシャールの日本の友人のひとり、隈研吾がデザインした蔵だ。

「富山との出会いをくれたのはケンゴだった。私は私のアイデアを前に進め、個人的なプロジェクト、あるいは夢を実現するための日本でのパートナーを探していた。それでケンゴに誰かいないか、と相談したんだ」
すると、この人しかいない、といって隈研吾が紹介したのが「桝田酒造店」の5代目、桝田隆一郎だった。
「ある週末に、ケンゴと一緒に富山に行って、マスダサンと会った。それで富山を案内してもらって、まさにここはうってつけだとおもった。富山は水も米も素晴らしい。そして、ほかの酒で有名な土地と比べた場合、それほどコンサバティブじゃないんだ。むしろ、外国人である私にもオープンで、起業家精神にあふれている。マスダサンもまさにそういう、革新性を持った人だった」
そこで3者は、挑戦をスタートしたという。リシャール・ジョフロワの日本酒のための蔵がデザインされていった。新しい蔵は理念的だ。
「蔵のコンセプトは歓迎だ。ここは要塞じゃない。象徴的なのは一つ屋根の下、1フロアに、酒造りの現場もオフィスもテイスティングができる土間も、すべてがあることだ」

最新のワイナリーみたいだろう? と言ったあと
「ただ、発想の原点にあるのは富山の南砺で見た大きなファームハウス(農家)。そこは、オーナー、フタッフ、農機具、収穫物、すべて一つの大きな屋根の下にあった。コミュニティ・ハウジングだったんだ。また、建物はそれが立地する地域のコミュニティの一部でもあった。これが「白岩」のスタイルだとおもった。私の蔵は『IWA5』を愉しむコミュニティの場になり、地元の人、働いてくれている人のコミュニティの場であり、そして、富山県立山町というコミュニティの一部でもある」

日本酒のトレンドへのリシャール・ジョフロワの回答
とはいえ、パンデミックの影響下、来日が制限されるなかで、リシャールは留守がちだった。そこに苦労はなかったのか?
「杜氏のヤブタは英語もフランス語も話さないし、コンピューターにも触らない。メッセージは彼の造った酒と手紙だけ。しかし、ヤブタは私が知る中でも飛び抜けて頭の切れる人物だ。私が何をしたいかを完全に分かっている。彼なしにはできないけれど、彼がいれば何も問題ない」
ヤブタこと藪田 眞人は、日本三大杜氏「丹波杜氏」のベテランという背景をもつ人物。リシャール・ジョフロワの片腕、というよりむしろリシャールがワインの雄なら、ヤブタは日本酒の雄といったところだろう。
この二人のベテランが造る日本酒は、現在の日本酒業界において、どのように自らを位置づけているのか?日本酒の造り手は若手が多い。彼らの新しい日本酒は、従来の日本酒より軽快で、さっぱりしていることが多く「飲みやすさ」という言葉がトレンドになっているように感じられる。
「それはキーになる概念だ。たしかに、日本酒のトップレンジの造り手は、流水の如酒を望んでいる傾向を私も感じる。それは日本の文化的な価値であり、また、日本酒のそういうスタイルを評価するのは日本人に限らないから、私がとやかくいう筋合いではないが……」
と少し言葉を探すようにしてから
「富山の水は硬すぎず、柔らかすぎない。それは私が望むスタイルに合っている。私は極度にドライな酒は望んでいないからだ。ドライであることへの偏重に私は同意しない。私はアッサンブラージュは理にかなっていると考えている……」
この発言には補足が必要だろう。日本酒、あるいは翻って日本の文化はピュアであることに価値を置きがちだ。極まった芸からは無駄が削ぎ落とされる。究極のシンプルこそが、技芸の極みである、という価値観だ。アッサンブラージュ、つまり、複数の要素をひとつの酒の中に混在させる、という方法論は、その観点からすると、雑。ピュアの対になる概念と考えられる可能性を多分にはらんでいる。リシャールはおそらく、それを言いたいのだろう。
「たとえば、私が造ってきたワインは、複雑だが、飲みにくくはなかったはずだ。メロー、スイート、ビター、サワー、うまみ、といった複数の変数をバランスさせる方法で、重力から解放されるからだ」
これはリシャールならではの哲学だ。リシャールはよく、やじろべえを例に出す。右手の重量と左手の重量が釣り合っているとき、やじろべえは重力から解放される。それは、左右どちらか片方がわずかでも重ければ、やじろべえはそちらに引かれて落ちる、つまり重力に捕まることから、逆説的に証明される。
「私は引き算ではなく、足し算で考える。アッサンブラージュはリッチでありながら、飲みやすい酒を生み出せる。複雑と飲みやすさは相反する概念ではない」
そして、個人的な企ての域を踏み出して「私が日本酒にもたらすことができるものがあるとするのならば、この考え方ではないか」とまで言う。
「日本酒がひとたび日本から足を踏み出したとき、そこを支配しているのはワインだ。いま、シャンパーニュやブルゴーニュの偉大なワインたちは、希少化と高騰化が止まらない。だから世界はワインに代わる偉大な酒を探している。それは日本酒だ。しかし、そこで日本酒はワインのルールで評価されてしまう。ワインの牢獄に入ってしまう。日本では酒は、切れがいいのが理想とされるかもしれない。しかし、日本の外では、余韻まで長く続く酒が評価される」
この事実を見落としてはいけない。と言う。
「ひとたび日本の外に出れば、日本酒は新参者だ。ほとんど知られていない。初めて日本酒を飲むフランス人が日本酒を評価するときに、どんな手がかりがあるだろう? 助けが必要なんだ。長い旅が、必要だ」
リシャール・ジョフロワの爪痕
酒にアッサンブラージュを施すということは、熟成させる、ということを同時に意味する。酒は混ぜてすぐには味も香りも舌触りも落ち着かない。ゆえに、リシャール・ジョフロワは、アッサンブラージュを持ち込むことで、熟成という概念も日本酒に持ち込んでいる。それはいわゆる「古酒」とは違うものだ。
「『IWA5』に決まったレシピはないが、今のところ、およそ18から20の大吟醸をブレンドしている。そして、リリースまで、18カ月、置いている」

これを聞けば、それは果たして日本酒なのか?という問いは当然、生まれるはずだ。
「ワインをやっているんじゃないか、と言う人もいるが……そうかもしれない。しかし私は日本酒を造っている。私は日本酒を包み込むものを押し広げようとしている」
それをやって、何を得ようとしているのか? リシャールの話はいよいよ、核心に近づく。
「懐を深くすることだ。日本酒があるシチュエーションを限定しないこと。日本酒とともにある食事を日本食に限る必要はまったくない。ニューヨークのモダンコリアンレストラン「Jungsik」のディナーはそういう意味でもエキサイティングだった。Jungsikのレストランに、日本酒は置いてないんだ。しかし『IWA5』とモダンコリアンとの組み合わせは、この世のものともおもえないほどに素晴らしかった。これまで、世界のどこでも味わったことのないものだった」
同じ『IWA5』でも『アッサンブラージュ1』と『2』と『3』とは、アッサンブラージュのやり方が違うから、それぞれまったく違う表情を見せるという。しかも『アッサンブラージュ1』であれば、リリース当時と比べて、2022年までに、さらに2年以上、熟成が進んでいる。そのため、熟成による深みも増している。日本酒がワイン的に熟成し、変化していくことを、リシャールは2019年に意図していたのか?
「年月がたって『IWA5』が変化していくことは、最初から織り込んでいた。私は、自分の酒を信頼していた。そしてそれは間違っていなかった。『アッサンブラージュ1』は、メローでコンプレックス。ブルゴーニュの赤ワインみたいな雰囲気といえるかもしれない。ビッグでボールドな肉やジビエとも合う」
そして、話はスタート地点に戻っていく。
「米から酒を造る文化はアジアには広くある。だから、そもそもアジアの食に、日本酒は合う。伝統的なヘヴィーな中華料理や辛い味にだって合う」
『IWA5』の相手は、フランス料理や、あるいはJungsikのようなボーダレスな新しい料理ばかりではない。日本酒がそもそも好相性であり、かつ、ワインでは合わない、とされている食事との相性は犠牲にされていない。
「日本酒は、いつだって、どこにだって、出て行ける酒なんだ。平和的征服(Peaceful Conquest)。世界中を射程圏内にとらえる。長い歴史のなかで最高峰の酒へと高められていて、そもそもポテンシャルを持っている。私が保証する。日本酒はもっと世界に出ていくべきだ。この旅はまだ始まったばかり。そして、この旅は最高にスリリングだ!」