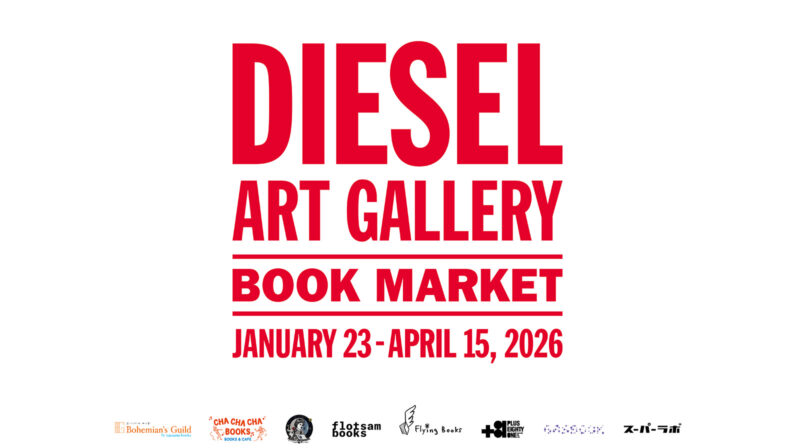正統派か、異端か。
視座によって正反対の議論を生むことがあり、時代によって真逆の価値を持つことことさえある。
今は世界的な日本酒ブランドとなった「獺祭」でおなじみの旭酒造は、精米歩合(米の削り度合い)を究極的に高めることで特段華やかな香りを醸す造りをもつ酒を作り上げた。1984年の立ち上げ当初は、地元山口の酒業界で異端とされていたその酒は、やがて、プレミアム日本酒の一大モデル・ケースとなった。
酒蔵にとって、日々新たな酒造りに挑戦し「変わり続けること」は大切な「哲学」と言える。しかし、それとは逆に「変わらないこと」にこだわり続けるのも大切な「哲学」である。
茨城県笠間・磯蔵酒造の酒造りは、誤解を恐れずにそれを表現するなら「究極の原点回帰主義」であり「個性的で異端」だ。
目指すのは、去年と変わらない酒
「うちは明治時代の酒造りをめざしているんだよ。」そう語ったのは、社長・礒貴大氏である。

「今年は去年と同じ酒を目指して、去年は一昨年と同じ酒を目指して、一昨年は・・・とその延長上に、当時の酒造りがあるって意味でね。」
日本酒業界は日進月歩、珍しい麹や酵母を積極的に取り入れ、テロワールなどワインに倣った概念を吸収し、販売においてはD2Cと、次々と新たな試みに走る中「時代の逆行」とも捉えられかねないその言葉がこの酒蔵らしい。
冷蔵技術の発達によって大手の酒蔵では「四季醸造」と言って通年造りを行うところも増えたが、磯蔵酒造では、昔の在り方に倣い、季節杜氏制の酒造りを行う。造りが始まれば、杜氏は蔵に寝泊まりし、麹米やもろみの番をする。季節が終われば、蔵から離れる。見守る人が変われば判断基準が変わってしまうからだ。
さらに、”限定給水”も徹底して行っている。その年の米の質や天候により、浸漬(米を水に漬ける作業)時間を毎日秒単位で管理する方法で、ストップウォッチを握りながら0.5%刻みで水分の調整を行う。
「今年はこんな感じで美味しくできましたっていうんだったらいいんですけど、毎年同じ味にしようとしてる酒蔵は、少なくとも麹米は全部限定吸水しないと駄目だと思います。うちは普通酒も麹米は全部限定給水しています。」
一見非効率に感じるが、”品質の一貫性”を重視しているからこそ必要なプロセスなのだ。
地に根ざし、地を醸す

「地産地消」
言い尽くされた言葉だが磯蔵酒造はそれを絵に描いたような酒蔵である。酒屋に並ぶ日本酒ラベルには「兵庫県産山田錦使用」など、米の産地が書かれているものが多い。しかし、かつては遠方から米を取り寄せて酒を造るという概念はなかった。地元の米を買い、地元の水で醸し、地元で消費する。これが酒蔵の「当たり前」だった。だからこの酒蔵は、地元・茨城の米にこだわる。



蔵の3箇所にかけられている半月のような絵。酒造りに不可欠な3要素を表しているそうで、黄色は米、青は水、赤は杜氏を意味する。
「地元の材料で作った地元のお酒は、地元でこそ飲まれるべきだと思うんです。だからウチの酒は、半径50キロ圏内ぐらいで、8割9割が消費されてます。」
そもそも、昭和の初め頃までは、人々が酒瓶を持ち、蔵に酒を買いに来ていた。近年では東京や海外向けのプレミアム酒に力を入れる酒蔵も多く「あの蔵は、遠くばかり見て、地元に門戸を開かなくなった。」なんて愚痴を地方の酒場で耳にしては、複雑な心境になることもある。
磯氏は続ける。
「昔は、その家の奥さんたちが「今日は秋刀魚の塩焼きだから、お酒は何がいいかしら」って近所の酒屋で聞けば、「おたくの亭主は、秋刀魚の塩焼きだったら、この酒をこのくらいの温度にしたら喜ぶよ」って教えてくれて、みんなオートクチュールのようにして酒を楽しんでたわけですよ。」
今や、個人商店の酒屋や飲食店が姿を消し、スーパーやコンビニ、チェーンの居酒屋が多くなりつつある。どこも同じように、東京などの大都市で売れている銘柄の酒を扱うようになり、その地域で造られている地酒に触れる機会も少なくなってきている。
「やっぱり誰かが僕らのものはこういうものでこういう思いで作ってるんだよっての伝えなきゃいけない。酒屋や飲食店が伝えてくれないんだったら、やっぱり自分でやるしかないんじゃないかなということで、今年の4月長年使っていなかった米蔵を改装して、ギャラリーとカフェスペースの真ん中に、酒販・試飲スペースを設けて入りやすくしたんです。」

酒器に現れる日本人の価値観
「おちょこがなんで小さいか分かりますか。」
蔵見学を終え、地元の陶芸家の作品である器で酒を飲みながら話している時、磯氏が言った。陶芸について造詣が深い彼は、酒器についての研究もしているのだという。

「ワイングラスで飲んだ方が日本酒も美味しいっていうのは一理あるんです。特に冷やしたものは。だけどそこがポイントなんです。日本酒の器は「自分自身がおいしく味わう」ということに特化されてないんです。」
確かにおちょこは、ワイングラスのように香りが広がる造りではない。そして容量も小さく他に実用性もない。ではなぜ酒器としてあの形状でありつづけるのか。
「おちょこは、注ぎ合うために小さいんです。一緒にお酒を飲み、お酒を注ぐという行為は、私は今あなたを思ってますよっていう心の表れなんですよ。なので何回も注ぎ合うためにわざわざ小さいので飲み干すんです。僕はこれが日本酒の文化のとても素晴らしいところだと思うんです。」
それを知ると、あの非効率的で、非論理的な小さな器と、それを手に酒を飲む人たちの姿がより愛おしい。
「明治時代の酒造り」と言った磯氏の言葉をあらためて考える。
彼が目指しているのは、「変わらぬうまい酒」であり「日本酒文化を後世に残す」ことなのではないか。日本中全ての蔵が、海外を意識した先進的で現代的な酒造りと楽しまれ方に移行してしまえば、日本人にとっての日本酒は失われていってしまうだろう。彼は現代の酒業界に果たすべき「役割」を買って出ているとも言える。そんなことを思いながら、あらためて磯蔵の酒「稲里」をいただく。
言葉ではうまく表現できぬが、やはりこの酒には「情緒」という味わいがある。