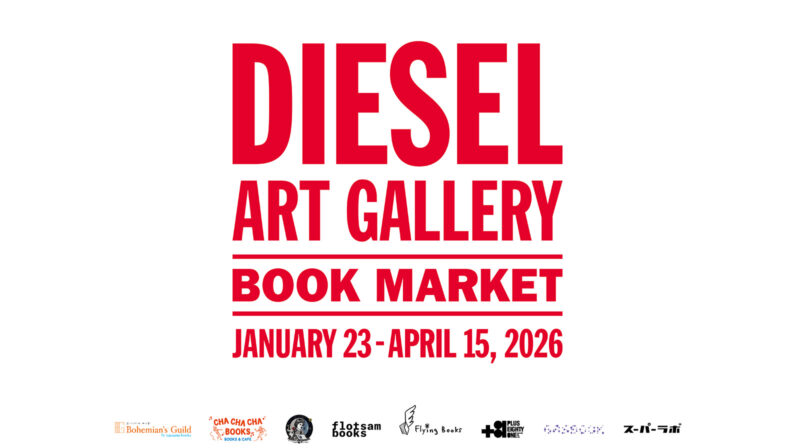一茶庵宗家佃一輝。サントリー美術館の茶室で江戸時代後期の陶工にして画家である文人・青木木米(1767〜1833)の作品を用いた煎茶会で。
日本の暮らしの中で「お茶」という言葉を使うとき、それは必ずしも抹茶のことではない。日本語はとても複雑だ。
趣味を問われて「お茶を習ってます」という場合の「お茶」は、茶道(侘び茶)の礼儀作法を指す。その場にあるのは、茶碗の中で茶筅(ちゃせん)を使って点(た)てる緑の抹茶。
映画を一緒に観たあとに「お茶しましょう」と言えば、それは喫茶店やカフェに行くこと。口にするのは、お茶であることの方が稀で、主にコーヒーか紅茶、時にはジュースまで含む。
家庭の食卓においての「お茶」は、私たちにとってもっとも日常的なもの。急須を使って茶葉から淹れたお茶で、多くの場合は煎茶かほうじ茶。近年では手軽なティーバッグを使う家庭も多いし、ペットボトルのお茶も含まれるかもしれない。
一方、海外に目を向けると、2000年代に入り急速に日本のお茶が注目されている。
背景には世界的な日本食ブームやヘルシー指向、コロナ禍中の巣ごもり需要などの複数の理由が挙げられるが、2023年の今、抹茶は、アメリカ、EUをはじめとする世界の多くの都市で、すでに寿司と同様の市民権を得たといえる。本場の日本で抹茶を味わってみたい、参加型アクティビティとして日本特有の文化である茶道をぜひ体験したい、と願う外国人観光客が増えているのも当然だ。
ところが、よくよく考えてみれば、お茶は茶樹も飲み方も淹れ方も、そもそも中国からの渡来文化。観光商品として消費されるほどにまで日本文化の象徴に発展した「茶道」とは、一体なんなのか?
“ 抹茶は、茶の湯という「おもてなし」の茶です。中でも洗練された形式が侘び茶です。侘び茶は、江戸中期に至って庶民の習い事、稽古事となって広がります。「おもてなし」の侘び茶作法は、江戸庶民の楽しみとマナーと社交を導きます。 ” (佃一輝『茶と日本人』より)
侘び茶(茶道)と、外国人にはほとんど知られていない文人茶(ぶんじんちゃ)いう二つの茶文化を通して日本文化、日本人について論じた書籍『茶と日本人』にはこう書かれている。この本の著者で、「文人茶」の伝承と再生をはかる「一茶庵宗家」の佃一輝氏にお話をうかがった。

—世界的に、日本のおもてなし文化として「ティーセレモニー」が注目されています。
佃:おもてなしの「侘び茶」作法は、ひとつの型があって、そこから人間とは何かという本質的なものに入っていこうっていう求心的なベクトルを持っているわけです。侘びというのはおそらく美意識なんだけど、中心にあるその美意識に向かって修行していく。そうやって型から入るのが日本人の特性として世界にアピールされているんだけども、実際には日本人の思考というのは全部がそうではない。いわば型外れなところ、型にはまらずいろんな意見をいえる、作法第一ではなく率直に意見をいい合えるという文化もあるわけなんです。
それが端的に現れるのが「文人茶」です。


木米「秋霽訪漁図」。サントリー美術館で行われていた「没後190年木米展」にも展示されていた作品がお茶会でも披露された。
同じお茶なんだけども、葉っぱを使って淹れるお茶は抽出時間が長いので、作法としてのお点前や、型をしている時間がすごく短い。その間に、掛け軸などの美術作品を見ながら、みんなで話し合って想像を広げていくというイマジネーションの遊びみたいなのが始まる。これが日本茶を使った、ある意味極めて日本的な文化のひとつ、文人茶なんですよ。
文人茶では、その場にある「美」みたいなものが拡散的に広がっていくと考えれば、侘び茶とはベクトルが逆方向ともいえますね。

木米作の急須で入れたお煎茶を木米の茶碗で頂くという特別な時間。木米の交趾焼(こうちやき)はなんとも品がいいと言う佃先生。そして、なんともお茶が淹れやすいのだとか。
—『茶と日本人』の中では、おもてなしの侘び茶に対して「文人茶は自娯のお茶」という表現をされています。
佃:人をもてなすには、まず自分が楽しまなくちゃ始まらない。ところが現代日本のおもてなし文化は、先生に教わった通り、「型」すなわちマナーをマニュアル通りにやることが良しとされているように感じますよね。
一方、文人茶というのは、基本的に自分のためにゆっくり淹れるお茶であって、人に淹れるお茶じゃない。元々は、官僚や文化人が書斎で自分のためのお茶を淹れて、ひとりで絵を描いたり鑑賞したり、作品を読んだり自分で書いてみたり。その合間にまたお茶を淹れて、ああ美味しいと勝手に楽しんでいるのが原点なんです。
そこにたまたま仲間が訪ねてきて、じゃあ一緒に喋ろうか、ついでにお前にもお茶を淹れてやるよ、と。これなんです。ただ自分が楽しんでいる。それを共有するのが、究極のおもてなしだと思いませんか。

木米の茶心壺(茶入れ)から木米が絵を描いている茶合(ちゃごう)へお茶を出して量をはかっている。茶合は茶器の一つで茶の量を測るもので煎茶用は二つ割りにした竹で作る。この木米の茶合は本のように二つ折りにする遊び心が詰まったもの。
—おもてなしのためのおもてなしではなく、私とあなたが楽しんでいることが良いおもてなしだと。
佃:そうなんです。ただしこのとき、私とあなたが論争や喧嘩にならないところが絶妙な面白さなんですよね。同じ絵を見て意見が違っても、この人はこういう感性なんだなと思う、それだけ。知性を持つもの同士、お互いの考えの違いがはっきり出るのが、逆にいいんです。


木米の染付の筆と急須。文人の集まりということで筆が文人茶のシンボル的なアイテムだそう。
英訳するなら「LITERARY GATHERING」。リテラリーとは「知的な、文学の」という意味ですから、お茶会ではなく、文人たちの会合、すなわち文会です。
Literary gathering with tea。文人茶は、人と人が「異なる」を自覚するという不思議なお茶なんです。
—外国人が文人茶を体験することで、日本を感じることはできるのでしょうか。
佃:「異なる」を自覚するためには、文学や美術を楽しむ、みんなで論じ合うことで基礎教養を高めることが必要ですよね。これはかつてヨーロッパでもコーヒーやワインを囲んで行われていたことなので、そういう意味ではグローバルです。

お煎茶の道具の飾り付け。(右上から)炉の上の急須、台に乗せられた急須、炉や炉の周りなどを清める羽箒、水指、茶合、茶心壺すべてが木米の作品。
たとえば、2019年に大阪でG20サミットが開催された際のパートナープログラムで文会をやらせていただいたんです。おそらく彼らは “ TEA CEREMONY ” だと思って参加されたのだろうけど、始まるとすぐにそうじゃないんだとわかるわけですよ。
すると、フィリップ氏(当時の英メイ首相の配偶者)がパッと音頭を取って「詩を作ろう」と提案されたかと思うと、イヴァンカ氏(当時の米トランプ首相の娘)が「私、もう詩ができたわよ」と応えたり。葉っぱでお茶を淹れている間のリラックスした時間を使って、洋の東西を問わず、年齢や肩書きも関係なく、こうして文化を比較して楽しめるのがいいんです。
人間、誰でもやっぱり365日働いてるだけじゃダメで。時代をさかのぼると、官僚や政治家といった人たちが仕事を離れ、書斎にこもってお茶を使ってひとりで楽しんだり、立場を忘れて仲間で楽しんだりしたのが文人茶の始まりです。マニュアルづくしの型にはまった組織の中で出世するとか威張るとか、そういうことから離れた世界。古典や現代アートというような、知らない世界、違う文化に接する豊かな機会がそこにはある。今、日本でも世界でも、そういう場やコミュニケーションが求められているように思いませんか。

文人茶では語らいが大切。
文化を比較することの楽しさは、江戸時代から始まっています。そういうことを日本茶を使って大きくやっているのが知的(リテラリー)で日本的という意味では、「それも」日本的だ、ということでしょう。
いわゆる世間一般にいう「日本には、特別にこういう茶道があるんです」というのとは、視点が逆なんだろうと思います。
—『茶と日本人』の中に、異国ぶりという言葉が出てきますが、つまり日本人は「異国ぶり」を突き詰めて「国ぶり」にするのが上手なんですかね。
佃:上手なんです。そして時々「国ぶり」が行き過ぎると、また突然「異国ぶり」が欲しくなり、ちょっと海外旅行にいってみたりする。そうしないと自分がおかしくなっちゃう。これって、すごいバランス感覚ですよね。実は、この対立項を両方含んでることこそが、日本的なんです。
事実としては、日本の場合は中国からお茶の文化を受け取って、長い歴史の中で時に反発もしながら「日本はこうだ」と育むうち、独自の文化(侘び茶という美意識)を作り上げた。だから、外国人のニーズによって抽出した「日本ぶり」のほうだけを「茶道です」と言ってみせても、実は日本が見えてこないでしょうね。
—文人茶のお稽古に参加してみたくなりました。
佃:はい、いつでもどうぞ。うちは家元制ではないですし、茶道のような師弟関係や免状制もありませんから、こんな世界があるんだと楽しんでもらえばいい。私と、私の仲間がリードしてる定例の稽古は、東京、大阪、京都、滋賀で開催しています。どこに来ていただいても楽しいですよ。

隈研吾氏が設計を手掛けたサントリー美術館の6階の美しい茶室「玄鳥庵」の露地。旧美術館から移築した。伝統とモダンが美しく融合している。
お稽古に継続的に参加している方は、男女半々といったところでしょうか。最近は美術関係者が多い傾向にあって、クリエイターだけでなく、学芸員、キュレーターと幅広く、40~50代の層が厚い。社会的にはもっとも多忙な世代が、自らのビジネススキルを上げながら文人茶の仲間になってくれるというのが一番面白い。僕らの世界を面白がって来てくれる人たちは、そういう元気さを持ってる気がしますよね。
考えてみれば江戸時代からずっと、広い教養を持つ、あるいはそういったことに興味を抱ける、特殊なリーダーたちが集まる世界なんだろうな、と思います。この知識人たちを昔も今も「文人」と呼ぶのでしょう。
—外国人でも参加できますか?
佃:もちろんです。事前にわかっていれば、こちららで通訳を用意することもできます。実際に、海外から年に1回来てくださる方もいらっしゃいますよ。ここ数年は大阪・関西万博を控えているというのもあって、行政や旅行会社からの問い合わせも多く、食事付きの文会ツアーも考案中です。
国籍も肩書も超えて、自分の中で違う世界の楽しみを見つける。煎茶を淹れるひとときが、そのよすがになればうれしいです。
文人茶は「おもてなし」の正反対にある、と佃一輝氏はいう。
“ ぜひ知っておいてもらいたいのは、「形と道とおもてなしのお茶」のほかに、「自娯と情と語らいのお茶」があって、二つが揃って日本の茶文化を形作っているということです、そこには「同じ」もあれば「異なる」もあり、対立を含んで併存し、どちらにも自在に行き来するという、しなやかな日本人の在りようがあるのです” (佃一輝『茶と日本人』より)
次にあなたが体験すべきは “ TEA CEREMONY ”? それとも、文人茶?

佃一輝
1952年大阪に生まれる。江戸後期以来、文人趣味の茶を伝える一茶庵宗家の当代。煎茶道とは異なる「文人茶」の伝承と再生をはかり、「文会」としての茶事を提唱。茶の湯文化学会理事。東京大学ヒューマニティーズセンター諮問委員。著書に『煎茶の旅~文人の足跡を訪ねて』『おいしいお茶9つの秘伝』『茶と日本人』など。
https://issa-an.com