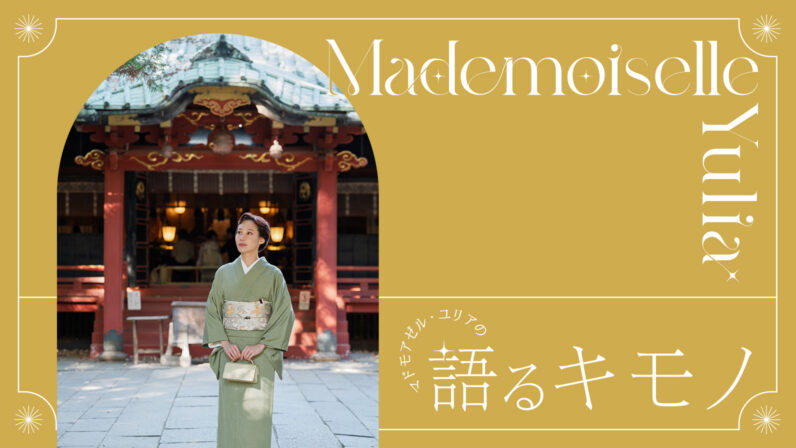20年以上クラブDJとして活動するDJ SHUNSUKEが、渋谷のディープなカルチャースポットを紹介する連載【Shibuya Deep Dive】。今回は、昭和26年(1951)創業。渋谷という街でカレーの記憶を刻み続けてきた超老舗店「ムルギー」。70年以上愛され続ける独特の味わいを求め、DJ SHUNSUKEが足を運んだ。今回はお店の歴史やこだわりなどをムルギーの三代目に当たる勝山友瑚さんに聞かせてもらった。

1951年、戦後復興の足音が響く渋谷の街に、一軒の小さな店が産声を上げた。店名は「エクリヤ」。後に「印度料理ムルギー」と名前を変えるこの店の始まりは、一人の鉱山技師・松岡憲策の海外での体験にあった。
ビルマで出会った味が原点に──ムルギー創業の背景
ムルギーの創業は1951年。三代目・勝山さんの祖父である松岡憲策さんによって始められた。
「祖父はもともと鉱山技師で、海外、特に当時のビルマ(現・ミャンマー)に鉱脈調査で出張に行くことが多かったそうなんです。そのときに、とある現地のカレー店と出会って、足繁く通ううちに店の方とも仲良くなって。おそらく、多少は作り方も教えてもらっていたんじゃないかと思います」
終戦後、渋谷に戻った松岡氏は、自らの体験を元に、日本人に合うように工夫を重ねたカレーを提供する「エクリヤ」を開業。後に店名は「印度料理ムルギー」となり、現在まで続く店の礎となった。

「今はカレー1本でやっていますが、当時はチキン料理やサラダ、カレーも種類がたくさんあったと聞いています。『印度料理ムルギー』という店名も、お客様にわかりやすいようにつけたそうで、その名残が今も看板に残っています」
ちなみに「ムルギー」とはヒンディー語で「鶏肉」という意味。とはいえ現在のメニュー構成や味から「インド料理じゃないですよね?」と言われることもしばしばあるそうだが、「祖父が掲げた看板をそのまま残したい」という思いから、あえて変えずにいるという。
ムルギー三代目が語る、家業を継ぐまでの道のり
ムルギーを継ごうと思った当初のきっかけについて、勝山さんは正直にこう振り返る。
「小さい頃は、‟こんな店なかったら良かったのに”って思っていました。というのも、ムルギーは母方の家業なので、父は会社員として仕事をしていたのですが、同時に母も店に立ち続けていたため、両親がいない家で留守番をしている時間が長く、寂しかったんです。父は大手企業に勤めていて特に生活に困っているわけでもないのに、なんで周りの家と違って、うちの母は朝から晩まで働いて、帰ってきたら僕たちのご飯を作って遅くまで家事をしなくちゃいけないんだろうと思ったりしました。寂しかったこともありますが、母にこんなに大変な思いをさせているお店だったり、そのお店を作った祖父に対しても、正直、よく思っていませんでした。」
創業者である祖父・松岡憲策さんは、勝山さんが生まれる前に亡くなっていたため、個人的な思い出もなく、幼少期から高校生までは、祖父やお店に対して複雑な感情を抱いていた。

そんな気持ちに変化が訪れたのは、大学生になってからのこと。母を手伝いたいという思いから、初めてムルギーの店頭に立った勝山さんは、来店する多くの常連客の存在に驚かされたという。
毎週決まった曜日に訪れる人、祖父の代から半世紀以上にわたり通う人、遠方からわざわざ足を運び行列に並ぶ人たち——。そうした光景を目の当たりにし、「こんなに多くの人に愛されているんだ」というのを肌で感じた。
そこで初めて、母が夢を諦めてまで守ろうとしていたものの大きさを理解できた気がしたという。そして、母の思いを無駄にしたくないという気持ちと、ムルギーを遺してくれた祖父への感謝の気持ちが芽生え、「この店を次の世代へと繋いでいきたい」という想いが生まれた。これが、家業を継ごうと決意した最初のきっかけだった。
幼少期の記憶と、家庭で味わったムルギー

勝山さんがムルギーのカレーを初めて食べたのは、小学校中〜高学年の頃。そのままでは辛すぎたため、母がマイルドにアレンジしてくれたものを食べていたという。「その味自体はすごくおいしくて、めちゃくちゃ好きでした。持って帰ってきてくれると嬉しかったですね」と語るように、家庭でのムルギーには特別な記憶がある。
お店に対して複雑な思いがあった幼少期も、「育ち盛りだったので、おいしいものには負けてしまいましたね」と笑って話す。中でも印象深かったのは、母がご飯とカレーをフライパンで炒めて作ってくれた“カレーピラフ”だったそうだ。「すっごいおいしかったんですよ」と当時を思い出す。
このピラフは、実は創業者・松岡憲策氏の時代に「カレーチャワル」という名前でメニューに存在していたものだった。母親も「食べたことはあるけれど、教わったわけではなく、自己流でなんとなく作っていただけ」と補足する。
現在では、メニューは「カレー」「カレーのトッピング」「サラダ」「ドリンク」とシンプルになっているが、先述にもあるようにかつては様々な料理が提供されていた。「昔は色々あったんだけど、今はもう消滅して、カレーだけ」と母が話すように、選択肢は絞られているが、そこに潔さを感じるとも言える。

「シンプルすぎますよね。これとこれなんて、タマゴあるかないかの差だし」と笑いながらも、現在のメニュー構成に愛着を持っている様子がうかがえる。
また、「ハヤシカリー」についても「これもベースは一緒なんですよ。辛いのが苦手な人向けにマイルドにしたメニューです」と説明する。「辛いのが好きでうちに来てるお客さんは、一回は食べるんですけど、絶対次から頼まないですね」と語るように、やはり“ムルギーカレー”の存在感は際立っている。
創業の味と盛り付けの継承
ムルギーの味づくりにおいて、最も大切にされているのは、創業者である祖父・松岡憲策氏の味を再現することだという。祖父から直接教えを受けたのは勝山さんの母のみであり、当時の指導はかなり感覚的なもので、再現には苦労したと話している。現在は、二代目である母と伯母がレシピの中で数値化できる部分を整理し、味のブレが出ないように工夫を重ねている。そうした努力により、長年にわたり「変わらない味」が守られている。

また、ムルギーの特徴的な盛り付けも創業当初から変わっていない。ライスを高く盛り上げた独特の形は、祖父・松岡憲策氏が山を好んでいたことに由来しているとされる。さらに、カレーにかかっている白い液体はミルクであり、「山の雪解け」をイメージしたものだという。
視覚的にも強い印象を与えるこの盛り付けは、他店のカレーとは一線を画す独自性を持っている。見た目のインパクトや雰囲気も含めて、ムルギーならではのスタイルとして受け継がれている。
なお、このライスの山の盛り方については、取材陣一同非常に気になるところであったが「企業秘密」とされている。
営業スタイルの変化と、変えないための判断
ムルギーが長い歴史のなかで変化せざるを得なかったことのひとつが「営業時間」だった。
創業当初、周囲に深夜営業の飲食店が少なかったこともあり、祖父・松岡憲策氏の時代は遅い時間まで営業を続けていた。勝山さんは「母も、子供の頃はお父さんが帰ってくるのがいつも遅かった、と言っていました」と当時の様子を語る。
創業者・松岡氏が病により現場を離れたのは約35年前のこと。当時、プロのカメラマンを志していた娘(現・勝山さんの母)が店を存続させるために進路を変更し、店を継ぐ決断をした。その後、勝山さんの伯母も加わり、姉妹2人で約30年以上にわたって店を支えてきた。
しかし二代目となった母と伯母の代では、それぞれ子育てや家事と両立しながらの営業となり、体力的にも時間的にも限界があったという。そのため「無理して体を壊してしまうより、“店を閉じずに続けていくこと”を優先して、営業時間を短縮するという判断をしたそうです」と話す。この流れの中で、ディナー営業は終了し、もともと金曜だけだった定休日も、火曜や祝日も休業に。営業体制は縮小傾向にあった。
ところが2025年から一部の曜日でディナー営業を再開するなど、営業の幅を少しずつ広げる動きが出てきている。「営業時間が伸びるのはおよそ30年ぶりということになります」と勝山さん。長年、減らすことはあっても増やすことができなかったなかでの転換となる。

営業時間短縮の影響もあり、営業中の来店密度が上がり、常連客を待たせることが多くなっていたという。そこにメディア露出が重なると、混雑はさらに激しくなるため、これまでは敢えて取材を受ける事を控えていたという。
「やっぱり母と伯母ががんばって続けてきたのも、“長年きてくれているお客様のため”という意識が強かったんです」と勝山さんは説明する。
「もちろん新しいお客様も大切ですが、常連さんがゆっくり食べられなくなったり、入れなくなっちゃうくらいなら、取材も受けたくないという判断だったんですよね」と語り、既存の顧客を大切にする姿勢が営業方針にも色濃く反映されてきた。
「どっちが大事か、という問題ではなく、全てのお客様が大事ではあるんですが」と前置きしつつも、ムルギーが大切にしてきた“守るための変化”がそこにあった。
味だけではない「ムルギー」の魅力 —— 二代目の人柄が築いた信頼
勝山さんが店に入り、母と伯母の姿を間近で見る中で実感したのは、「味や盛り付け、メニューを守ることはもちろん大前提だが、それ以上に、長く店が続いてきた一番の理由は二人の人柄にある」ということだった。
「母も伯母も“お母さん”なんですよね。いい意味でとにかく“おせっかい”。」
客との距離が近く、仕事や子育ての状況、体調なども自然に気にかける。小さな子どもを連れた客には、頼まれてもいないのに「これ食べたら?」とご飯にふりかけを添えて出すこともあるという。

また、ムルギーはもともとご飯の量が多めだが、少なめに注文した客に対しても「本当に足りるの?」と何度も確認することがあるという。「いっぱい食べさせたいのがお母さんなのかな」と勝山さんは語る。
「僕は『鬱陶しがられるかも』と気にしてしまって言えないことでも、母と伯母は、お客様のためになると思ったことを自分がどう思われようとやり抜く。そこに嘘がないから、お客様に愛されてきたんだと思います」
実際、二代目の代になってから営業時間は短縮傾向にあったが、それでも「しょうがないね、続けてくれるだけでいいよ」と客から理解され、変わらず通い続ける人たちがいた。「二代目の偉大さは、そういう関係性を築けたことだと思っています」
現在、勝山さんは三代目としてムルギーの運営に加わっている。ただし、母と伯母も現役で店に立っているため、「代替わり」というよりは「継承の流れの中にある」と位置づけている。その中で「味だけでなく、お客様への思いも、母と伯母からしっかり学んで受け継いでいきたい」と語る。接客の姿勢もまた大切な継承の一部だと考えている。

渋谷の「帰る場所」として —— ムルギーが目指すこれから
勝山さんは「ふとしたときに“帰ってきたい”と思ってもらえるような場所でありたいんです」と語る。ムルギーを単なる飲食店ではなく、誰かにとっての「渋谷の中の故郷」として残していきたいという。
勝山さんが引き継いだのは、レシピや経営だけではない。何十年も通い続ける常連客や、毎週欠かさず訪れる人、学生時代の思い出とともにムルギーがあると話す人たち——そんなお客様一人ひとりの「思い出」そのものも、確かに受け継いでいると感じている。

「渋谷って、日本の中でも特に変化が激しい街じゃないですか。その中で、70年以上も変わらず同じ場所で店を続けてきたということに、最大の意味があると思っています」
例えば、久しぶりに渋谷を訪れた人が、様変わりした街並みに驚き、少し寂しさを覚えることもあるだろう。だが、ムルギーのように「変わらない味」を守り続けている場所があれば、過去の渋谷の記憶が蘇り、「懐かしい」「落ち着く」「またがんばろう」と、前向きな気持ちになれる。そんな心のよりどころとしての存在を目指している。
「これからは、“渋谷のカレー”“渋谷の定番”として、街の中でのブランド価値をもっと高めていきたい。そして、より多くの人が“帰ってこれる”場所になれたらと思っています。いずれは、創業100年を迎えることが目標です」
100年、そしてその先へ
三代目である勝山氏が継承したのは、創業者・松岡憲策氏の味だけではない。二代目である母と伯母が守り続けた想いや、人とのつながり、そして店の空気そのものである。
それらを未来へと受け継ぎながら、ムルギーは「渋谷の中の故郷」として、これからも人々を迎え入れていく。
創業から70余年。次なる節目である100年に向けて、ムルギーの物語は、静かに、そして力強く続いていく。

ムルギー
住所:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目19−2
営業日:月、火、水、木 (土・日ランチのみ)
ランチ:11:30~15:00
ディナー:17:00 〜 21:00
定休日:金・祝
Webサイト:https://murugi.co.jp/
Instagram:@murugi1951