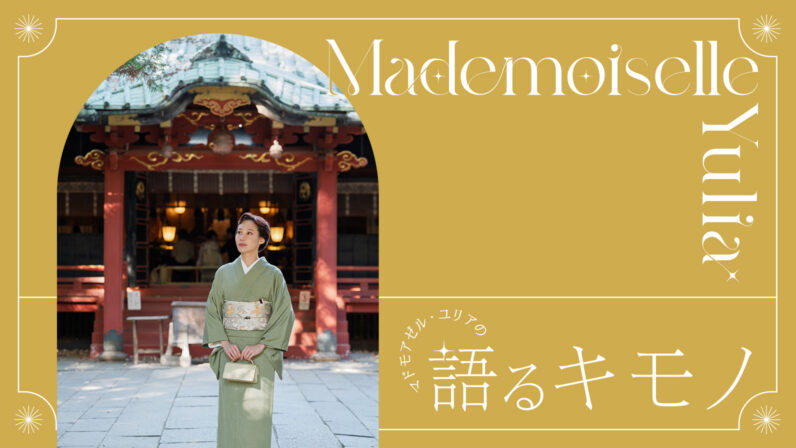日本の伝統食材で身近なものの一つに麸(ふ)がある。これは、小麦粉からでんぷんを取り除いた小麦たんぱくを主原料としたもので、様々な種類がある。日本人の食生活の変化に伴い、消費量が減少した麸だが、近年は国内外でその価値が見直されつつある。
麸の魅力はどこにあるのだろうか? そのヒントを探るべく、麸の専門店、半兵衛麸(はんべえふ)本店を訪ねた。

半兵衛麸本店の入り口
江戸時代創業としては数少ない麸屋
麸の歴史は古い。株式会社半兵衛麸の女将、玉置淳さんの説明によると、もともとは中国が発祥の地。室町時代、修行先の中国から京都に帰ってきた僧によって、日本に伝えられたという。
玉置さんは、話を続ける。
「そこから日本独自の発展をして、焼き麸や生麸などいろいろな種類を作るようになりました。当初は、修行僧向けの精進料理の素材でしたし、京都から全国に広まるのも徐々にでした。江戸時代に入って普及し、町民も食べるようになりました。その頃は、すき焼きや味噌汁に入れる焼き麸が主だったようです」
明治時代以降は洋食化が進み、麸の存在感は次第に薄れていった。現在では、ごく小規模経営の店や企業が製造の主体。ほぼ、麸専業でありながら、半兵衛麸のような規模の企業は珍しいという。また、半兵衛麸は、元禄2年(1689年)創業と、長い歴史をもつ点でも際立っている。本店ビルは新しさを感じるが、店内のそこかしこに、かつて製造に用いられた道具が安置されている。

麸の製造に使われた道具類の一部
創作色豊かな麸製品の数々
筆者の少年期の思い出だが、味噌汁の具によく麸が入っていて、汁が浸み込んだ不思議な食感がたまらなく好きであった。しかし、今の若者で、麸に親しんでいる人はあまり見かけない。麸は、時代の波に呑まれ消えゆく運命にあるのだろうか……。半兵衛麸で販売されている、伝統的な麸製品の数々を見ながら、ふとそう思った。しかし、玉置さんは、そうはならないと言う。
「肉を食べない修行僧には、貴重なたんぱく源でした。そういう意味では、とてもヘルシーな食材なので、健康志向の現代人にこそピッタリなんです。それでも、今では認知度も低いので、まずは食べていただけるように工夫と提案をしています」
「工夫と提案」の一つが、ハイアットリージェンシー京都のパティシエとコラボして誕生した、麸のクッキー「玉 -TAMA-」だ。いちご、ゆず、抹茶、和三盆、ほうじ茶の5種類の味があり、いずれもアーモンドパウダーが隠し味的に使われている。

パティシエとコラボして生まれた「玉 -TAMA-」
玉置さんから5個入りの1箱を頂戴し、さっそく食べてみる。口の中で、ほろほろと甘くほどけるような食感が美味しい。それまで麸に対して持っていた、素朴一辺倒なイメージが覆される体験だ。
本店ビルの1階は、広々とした販売エリアとなっている。見て回ると、伝統的なものと並んで「麸まんじゅう」「さくらもち麸」「ふぃナンシェ」といった、創作色豊かな麸製品がある。来店客は若い女性も多く、決して麸が廃れつつある食材ではないことがうかがえる。

本店1階の売り場には麸を使ったさまざまな製品が並ぶ
さらに、半兵衛麸が最近行った大きな取り組みが、本店3階にある「Cafeふふふあん」だ。2022年4月にオープンしたこのカフェでは、なま麸や湯葉などをベースにした料理やデザートが提供されている。ガラス張りの店内は明るく、席数も約70席あって、ゆったりした雰囲気に包まれている。窓外には、鴨川や五条大橋が見える。このカフェも、麸の世界を広く知ってほしいという願いが具現化したものだ。

「Cafeふふふあん」の「FuFuマ麸ィン」
豪華なお弁当箱を収蔵した博物館も
半兵衛麸本店ビルは現代的なガラス張りのビルだが、隣接する昭和期に建てられた洋館には、麩と湯葉の料理を供する「茶房 半兵衛」がある。さらには、もっと古い明治期の京町家も隣接している。



1枚目:「茶房 半兵衛」の入る昭和期からある洋館
2枚目:京町家造りの建物
3枚目:3つの建物で囲まれた中庭
これら3つの建物に囲まれた中庭を通って京町家に入ると、意外な見どころに出合う。それが、「お辨當(べんとうばこ)箱博物館」だ。その名のとおり、主に江戸時代後期のお弁当箱や酒器が陳列されているミニ博物館。以前の代の当主が、骨董屋を巡って蒐集したもので、豪華さに目を見張る。

これらは、当時の富裕層や公家が使ったものだという。彼らは、行楽のおり、贅を尽くした蒔絵や螺鈿の細工を施した弁当箱を持参した。蛍狩りの際は、蛍の意匠が散りばめられた弁当箱、舟遊びの際は、舟の形を模した弁当箱というふうに、そのこだわりは現代人の比ではない。

舟の形をした珍しい弁当箱
今の日本でも、手間をかけ弁当を作る文化は息づいており、海外でも「BENTO」として注目されているほどだ。現代の弁当箱の大半は簡素なものだが、きらびやかで知られざるルーツをたどってみるのも、また一興だろう。
再び売り場に戻ると、販売の品とは別のものが陳列されているのが目に入った。近寄ってみると、形も様々な木製の弁当箱であった。京都芸術大学の学生、満生琴音(まんしょう ことね)さんの作品だという。「京都芸大の学生さんのフィールドワークとして活用いただいたご縁」で展示したという(現在は展示終了)。

満生琴音さんの作品
このように、単なる食材の製造・販売にとどまらない魅力が詰まっているのが、半兵衛麸だ。近辺の観光地を訪ねるつもりなら、旅程の一つに組み込んでみてはいかがだろうか? きっと、予想もしない発見があるはず。
半兵衛麸
住所:〒605-0903京都市東山区問屋町通五条下る上人町433
営業時間:10:00~17:00
定休日:水曜日
Webサイト:https://www.hanbey.co.jp
Instagram:@hanbey1689